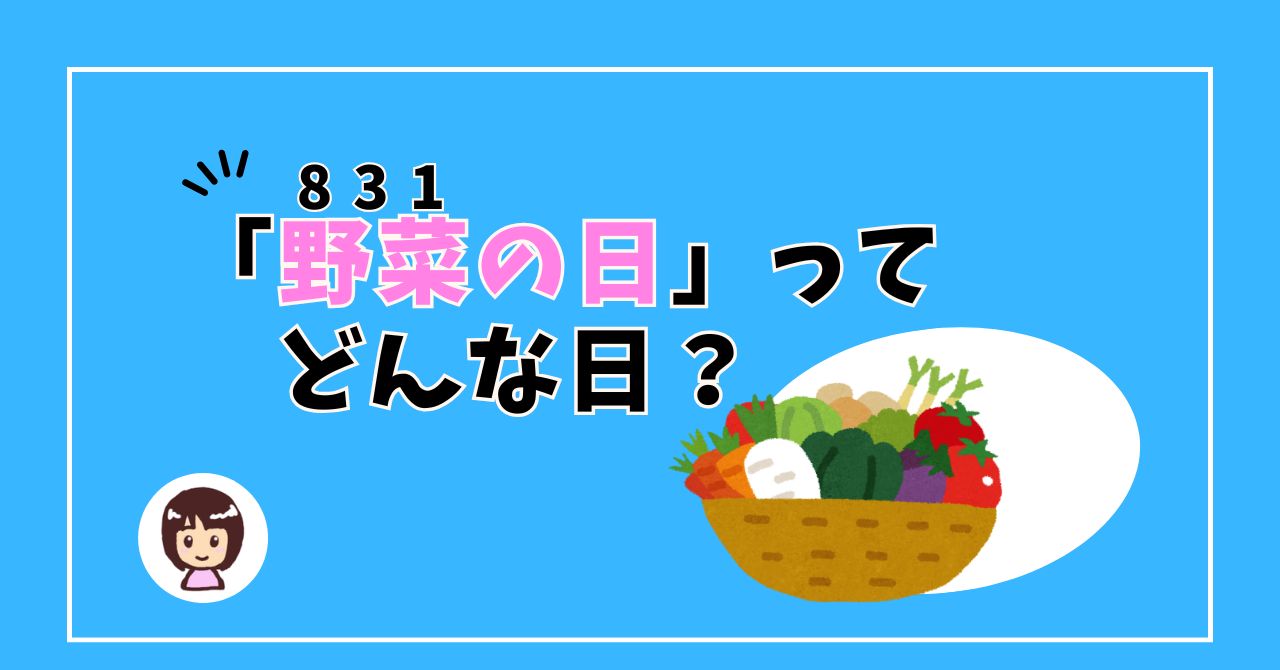「野菜の日」ってどんな日?
野菜の日とは?
「野菜の日」は、毎年8月31日です。
これは、1983(昭和58)年、全国青果物商業協同組合連合会、食料品流通改善協会などを含む9つの団体によって制定されました。
野菜の良さや栄養価値を再認識し、もっと野菜を食べてもらうことを目的に制定された記念日です。

なぜ8月31日なの?
この日付は、語呂合わせから来ています。
- 8(や)
- 3(さ)
- 1(い)
これをつなげて読むと「やさい」となるため、8月31日が「野菜の日」とされました。
「野菜の日」の目的
「野菜の日」の主な目的は、野菜の美味しさや栄養価に関する魅力を伝え、国民の野菜摂取量を増やすことです。
野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維などが豊富に含まれており、生活習慣病の予防や免疫力の向上など、健康維持に欠かせない食品とされています。
「野菜の日」には何が行われるの?
「野菜の日」は国民の祝日ではありませんが、この日に合わせて様々な活動が行われます。
- スーパーや八百屋での特売: 野菜のセールやキャンペーンが実施されることが多いです。
- 飲食店での特別メニュー: 野菜をふんだんに使った限定メニューが提供されることがあります。
- メディアでの特集: テレビや雑誌、ウェブサイトなどで、野菜のレシピや健康効果に関する特集が組まれます。
日本人の野菜摂取量の現状と課題
厚生労働省が実施している「国民健康・栄養調査」の結果を見ると、日本人の野菜摂取量は目標量に達しておらず、減少傾向です。
目標量との乖離
厚生労働省が提唱する「健康日本21(第二次)」では、生活習慣病を予防し健康を維持するために、成人1人1日あたりの野菜摂取目標量を350gとしています。しかし、実際の平均摂取量はこれを大きく下回っています。
- 令和5年(2023年)の調査結果: 20歳以上の野菜摂取量の平均値は256.0gです(男性262.2g、女性250.6g)。これは目標の350gに約94g不足していることになります。
- 過去10年間の推移: 直近10年間で、男女ともに野菜摂取量が有意に減少していることが指摘されています。

このため、厚生労働省などが、普段の食事に
「副菜を1品追加しましょう」というアドバイスをしています
年代別の傾向
- 若い世代での不足: 特に20歳代から40歳代の若い世代で野菜摂取量が少ない傾向にあります。
- 高齢層での比較的高い摂取量: 60歳以上では、若い世代に比べて野菜を比較的多く摂取しています。しかし、それでも目標量には達していません。
社会経済・国際間での比較
- 社会経済状況との関連:野菜は相対的にみて高価な場合が多く、所得が低い世帯と、所得が高い世帯と比較すると、野菜摂取量が有意に少ないことが示されています。
- 国際比較:
- 日本人の野菜摂取量は、欧米諸国と比較しても低い水準にあります。例えば、中国(766g)、ギリシャ(659g)、韓国(548g)などに比べると、大きく下回っています。
- かつては「肉食」のイメージが強かったアメリカと比較しても、近年では日本人の摂取量がアメリカを下回る場合があるという指摘もあります。
野菜摂取量不足の背景にある要因
- 食の簡便化志向: 忙しい現代において、「手軽に食事を済ませたいという」志向が高まり、外食や加工調理品の利用が増えています。これらは、家庭での調理に比べて野菜の摂取量が不足しがちといわれます。
- 食に関する意識の低さ: 特に若い世代では、1日に必要な野菜の量を知らない、あるいは健康的な食生活への関心が低い場合があります。
- 食料自給率の低下: 野菜の消費動向全体として、減少傾向にあります。